【面接や転職にも使える】状況別クレーム対応問答集!実践してきたスキルと共に紹介
こんにちは。スキラゲックス(Twitter:@skillagex)です。
この問答集は日々クレーム対応を行うなかで考えられるケースをフロー別に分けたものです。
これからお客様の各種お問合せに対応するにあたって、考え方や行動の移し方を参考にしていただければと思います。
またこれから不良や返品の対応をされる方、公務員の面接で対策を考えている方にも参考になればと思います。
- お問い合わせ、クレーム対応をする方、また経営者の方
- クレーム対応にてこずっている人
- 営業中にクレーム対応をされる方
- これから不良や返品の対応をされる方・公務員の面接で対策を考えている方
以上の方におすすめの記事です。
まずはじめに心構え
お客さまを待たせないことも大切ですが、クレームに関しては誠意と謝辞を優先します。解決策はその点においては後の対応になります。
また受ける我々のメンタルケアも重要です。人ってクレームに弱いので準備と対策が必要です。
人間は基本的に文句や苦情に対して精神的に弱く、極力避けたい生き物なので、何も心構えをせず受けてしまうと必ず傷つきます。
なるべく傷つかないように、準備しておくコトが大切です。
クレームの基本をおさらい
もとめられるクレーム回答とはなにか
僕が考えるに、クレーム対応とは 1つ1つの寄せられた問題に対して真摯に対応していくことが大切な職務だと考えます。
その一つ一つの対応でリピーターになるか二度と買わない方になるか、大きく結果は変わってきます。
とはいえ対応は多岐にわたるため、その場で答えられない事は持ちかえって相談したりして、時間がかかるものだと思います。一つ一つ即答できる完璧超人を目指すのではなく、相手を安心させる手順をしっかり踏まえることが大切です。
クレーム発生のフロー
以下のような順序を踏みます。
- 商品の購入
- 問題の発生
- クレーム
- 検討・対策
- 報告
- 終了(再発防止に向け観測)
または
- 問題の発生による通常の行いが困難な場合が発生
- クレーム
- 検討・対策
- 報告
- 終了(再発防止に向け観測)
問題の発生からクレームまでの連絡は早く、解決が早ければ早いほど問題の複雑化は避けられる傾向にあります。
クレームの発生時の人の動き
想定外の不利益や不便が起きた時、人は周りに助けを求めます。
頼れる人が近いとその人に発信します。誰に相談していいか分からないときは電話やネットで担当者を探します。
初めてクレームの場合は周りに相談してからクレームを入れることもあり、周りに聞いた情報を頼りに質問してくることがあるので、まず自社(自分たち)の対応ルールを説明していく必要があります。
クレームの解決
最終的にどんな結末であれ、お客様が納得いかなければ未解決であり、納得がいけば解決です。
ご納得いくまで要望を聞き、ただし何でもOKというわけではないので納得いただける条件を提示しながら落としどころを探ります。
- 交換
- 返金
- 情報の開示
- 示談
- 報告のみ
しかし恐喝や恫喝まがいのクレームに対しては毅然と対応しなければなりません。社長を出せ!に応じることは出来ませんよね。
事前に録音の承諾を得る、連絡したことの履歴、また弁護士などにも相談できるよう、あらかじめ関係各社へのパイプ確認をとっておきましょう。
まずなぜクレームが起きるのか?クレームの原因は主に3つ
こじらせるときは原因が必ずあります。お客様の状況は以下のような場合が多いかと思います。
- 想定外の事が起きたので何とかしてほしい
- ずっと困っている、言っているのに対応してくれない
- 以前ひどい対応をされた
経験上、対応がこじれて大変な目に合っているのは2番目と3番目のこじらせた場合です。
どちらにも共通しているのは「誠実さを欠いた行動をこちらが取った」ことにあります。
そうならないように普段細心の注意を払って日々のクレーム対応をしていると言っても過言ではありません。実は対応力・行動力とかより聞き取り力が重要になってきます。
再発防止を考えるのであれば、「最初の受け答えをマニュアル化」して、人によって対応が変わらない受け答えができるよう、ケースごとにどう対応するか流れを書き記しておくとスムーズです。
クレームに対して準備するモノ・必要なモノ
全員で統一した対応ルール、取り決めのマニュアル
クレーム対策で問題なのはシミュレーション不足によるお客様へのいい加減な返答です。
「多分」とか「分かりかねます」では相手を苛立たせてしまいますので避ける、など基本的な受注対応方法から、この場合はこう対応するという大筋のシュミレートです。対応者の皆で共有できるようルールブック化した方がいいと思います。
状況確認聞き取りアンケート
メモ帳も各自自由にとるのではなく、決まった項目が書き込まれたメモ帳を共通して使う方が、聞き漏れを防ぐことができます。
お客様の名前、電話番号、必要ならご住所など個人情報のメモ
こちらのデータベースに登録があったとしても、しっかりと記録させてもらうようにします。
違うケータイ番号かもしれませんし、恐喝まがいのクレームには効き目がある場合も。
情報のファイリング、もしくは記録できるデータベース
これら聞き取りした情報を蓄積しておく堅牢な管理システムが必要です。
販売システムもあるのなら連携できるような柔軟なカスタマイズができるデータベーススシテムが望ましいです。
対応フローを構築しておく
- 連絡を受ける
- 社内で共有する
- 対策を検討する
これらの流れがあやふやだと、失敗しても学ばない社内体制になってしまいます。
連絡者に報告、もしくは途中経経過を報告する
クレーム報告者に結果と対応を報告、もしくは途中経過でもいいので必ず連絡を入れます。
終わってから連絡していい場合と、逐一報告しないと不安に駆られて逆上されるパターンがあるので慎重に見極めて対応しましょう。
電話は録音対応にする
万が一のため録音機能は持たせた電話を導入しましょう。
事前に「この通話は録音します」という案内を入れることで、電話口の相手のトーンを下げてくれる効果もあります。
被った損益を正しく導き出し、再発防止の影響力を持たせる
必ず責任の所在を突き止め、再発防止に努めるよう、厳しく罰せねばなりません。
その権限は社長しか下せないので、社長が罰する勇気を持たなければ改善はされません。
何事もなかったかのように済んでいるのは一見無事に終わってめでたし、のようにも見えますが、社長がそれをスルーしてしまうと部下はやる気を失いますし、発生させた部署はお咎めなしとして増長します。
社長を動かすにはどうしたらいいか?要はどれだけ損を被ったかを報告すればいいのです。管理者は金額には厳しいので、ようやくことの重大さがわかってくるのです。
対応中に心がけることは
クレーム対応は以下のやり方を特に求められることが多いかと思います。面接官も欲しがっている答えかと思いますので、対応の心構えとして常に持っておきましょう。
最後までしっかり聞く
大事なことは「話を最初から最後まで聞く」「途中遮ったり反論しない」「私は貴方の意見をしっかり聞いています。」「落としどころはどこか」を考える姿勢です。
何を求めているか、落としどころを提案出来るようにする
日本人は京都民程ではないにせよ、モノの伝え方が「はんなり」しています。
少し遠回りで直接的な伝え方を嫌がる人もいます。お怒りの場合は自分が何を伝えたいか、まとまってないまま話す方もいらっしゃるので、落ち着くまで聞く必要があります。
こういった場合、直接要望を聞くと相手は伝えているつもりになっているのでお怒りになる可能性があります。聞く側としては要点がはっきりしないので仕方がないのですが、会話の途中で「つまりおっしゃる〇〇はこういうことでしょうか?」と質問の意図を明確にしながら話を進めるのが聞き上手になるコツです。
・自分では判断できない場合、一度持ち帰り上司に相談する旨を伝える
クレーム対応をするうえで役立った手法
パニックにならない感情を込める 棒読みよりも抑揚を付けてしゃべった方がこちらの「申し訳なさ」は伝わります。やりすぎると苦笑が返って来ますが、それくらいでもいいと僕は思ってます。電話なら特に顔が見えない分、こちらの想いを伝えるには必要なテクニックだと思います。
共感する
相手の信頼や安心を勝ち取るには共感も有効な手段です。
「分かります」は結構お話をまろやかにするキラーフレーズだと思います。もちろん分からないのに無理して分かりますという必要はありません。いっそ会社を相手に「僕もどうかと思うんです」と言うくらい共感すると、相手も分かってくれてる、味方だと感じてからやすいです。
また「大変でしたね」「お察しいたします」の一言が挟めるとより共感度が増し、相手の信頼を得やすいように思います。
自分で判断できないことは一度持ち帰る
即答できないことは一度持ち帰って相談すると言いましょう。「持ち帰って検討」もいいですが、 最初の慣れないうちは「持ち帰って上(上司)と相談する」の方が相手からの信用も増すのでおすすめです。
ケースバイケースなので即答しようとはせず、一度検討のため意見を持ち帰るという行動を取った方が「きちんと考えようとしてくれ ている」という印象を持たれます。
朝方電話する
理由はなるべく午前中のほうがお待たせすることがないからです。
後は予定が入っていないので捕まえやすい、忙しくなる前だから話しやすいなど。これは経験上の予測です。
クレーム内容をヒアリングするポイント
ヒアリング時に聞き取っておきたいことは以下の通り。
- お名前
- 連絡先
- 問題の詳細
- 発生時期
- ケガの有無
- 過失・損失の有無
- 他にも問題は無いか
- 解答の期限(いつ回答して良いか)
特に最後の回答期限は、双方確認しておかないとトラブルにつながります。
いつならお電話してよろしいですかと聞いて、帰ってきた答えが期限になることが経験上多いです。
クレーム受け取り後のフロー
問題を細分化、フローにして小問題に抽出する
起きた問題に対して、できるだけ問題を細かく切り分けて、原因と対策を練っていきます。
ネットショップであれば、問題が破損であっても、自社の管理の問題なのか?輸送中の破損なら梱包の問題?もしくは運送会社の問題?いろいろ考えられますよね。
ヒアリングの時に破損の中身を詳しく聞くか、返品をお願いして確認します。
そしてどこを改善・変更すれば効果が高いか吟味していきます。
効果のある改善を優先的に行う
全て改善していては時間がかかりすぎる場合があります。
効果が出て対策として十分と判断できる、一番効率よく効果が出せそうな範囲から手をつけていきます。
関係各所に連絡を取る
問題解決に向け、影響のある方々に連絡をし、どうしたら解決できるか相談をします。
何で悩んでいるかをしっかり聞いておくことで、どこで妥協できるかも調節がしやすいかと思います。
対策案と実施案を決定
自分が最終決定者なら話が早いのですが、上司に問題と改善策を提案する場合もありますよね。
だいたいお金の話が絡んでくるので、得られる効果としなかった場合のデメリットをクレーム対応時間と経費で説明するとスムーズです。
改善、または施行次第 お客様に報告する
ご連絡いただいた連絡者に報告します。
この報告が遅いと不安にさせたり二度と利用してくれ なくなったりするので、解決してなくても途中報告という形で連絡をとるといいでしょう。
無事解決すると喜ばれるのはもちろん、オンラインショップのお客様なら貴重なリピーター顧客になってくれる可能性も高まります。
一度迷惑をかけているのですが、こちらの対応がいいといいお店だと感じてくれるのです。
クレームを防ぐ対策を打つ
同じようなクレームが続いているなら、再発防止に向け先手を打ちクレームの元を立つことが重要です。
今後も同じ過ちが発生しないように、販売前・リリース前のチェック項目に確認ポイントを加えておきましょう。
その後の効果実証・計測を行う
解決した後の計測は忘れがちですが重要です。
なかなか行われないことが多いかと思いますが、しっかりと計測しておくと、改善に対してどれくらいの効果が見込めるか数字で分かるようになってくるので、次からのスピーディーなクレーム対応に役立ちます。
自分のメンタルケアも重要!
クレーム対応者は真面目すぎます。休息も必要です。
それゆえ任されているということもありますが、貴方が思っている以上に心身ともにダメージを負っています。
こんな場末のクレーム対応ブログを見にきている貴方はきっと真面目すぎるのです。自分のメンタルは自分で守るしかありません。息を抜くのも仕事のうちなので今のうちに仕事のメリハリの付け方を一緒に覚えましょう。
クレーム対応のまとめ
クレーム対応には正解はあってないようなもの。
その場の対応力は少しづつ経験で磨かれるものがあるので、少しづつブラッシュアップして、原因を突き止められたら再発防止に向けどうやったら動けるか、対応策を考え実行に移していきましょう。






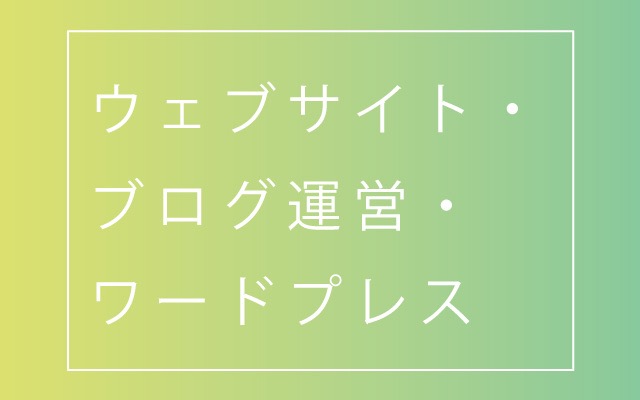
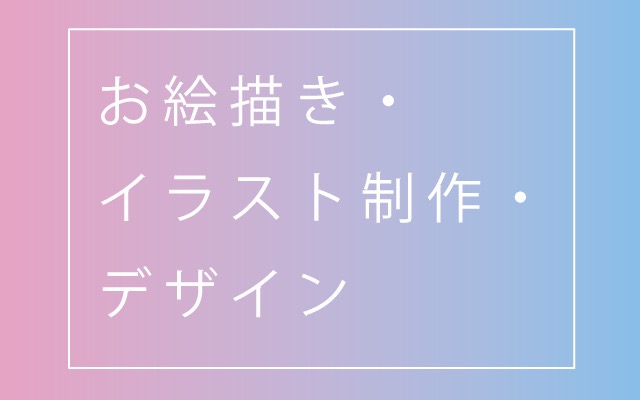
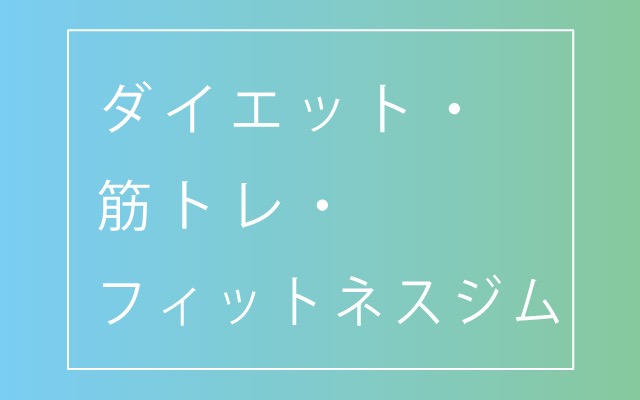
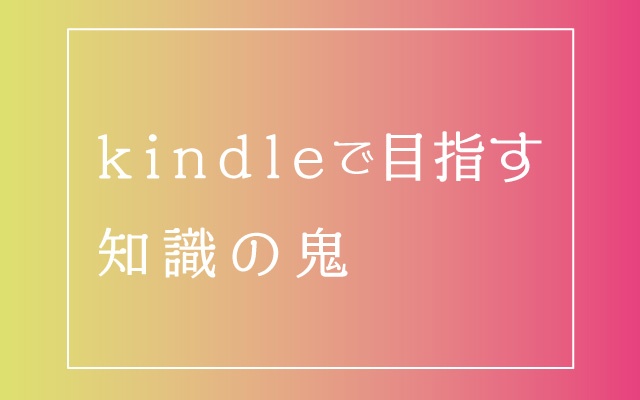










ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません